はじめに
情報量基準の復讐も兼ねて簡単にまとめます。
こちらの内容をまとめたものです。
事前設定
ある確率モデルとデータから得られた予測分布と真の分布
との違いを表現する交差エントロピーをはんか誤差とよび、次のように定義され変形される
また経験損失を予測分布から次にように計算することができる。
AIC
AICを検討する際に次の要素を仮定する
真の分布は想定される確率モデルの中に含まれる
サンプルはi.i.d
は確率モデルについて正則である
最尤推定値をもとにした予測分布は次にようになります。
この時の汎化誤差は平均対数尤度の符号を反転させたものに一致する。
これは予測の良さを表現すると言える。
一方、経験損失は次のように最大対数尤度の倍したものと算出できる。
ここで、予測分布の導出に利用したデータと同じデータで経験損失を算出しており、そこにはバイアスが存在している。
データの元でのバイアスは次のようになる。
もし、新たに予測する確率変数とするデータを与えられた時、偏りの期待値は次のように表現できる。
この二つの損失のバイアスの期待値は、真の分布は想定される確率モデルの中に含まれるという仮定の元で、漸近的にに従うことが知られている。
このことからAICは次のように定義される。
詳細は、北川の3.4に記載されている。
WAIC
WAICではベイズモデルにおける汎化損失の推定を考えていきます。
このときに、以下を仮定しています。
真の分布は想定される確率モデルの中に含まれなくて良い
サンプルはi.i.d
は確率モデルについて必ずしも正則でなくても仮定
ベイズ推定により得られた予測分布は確率モデルを事後分布により、次のように得られる。
ベイズ予測分布の汎化損失は次のようになります。
次に経験損失は、次のようになる。
AICと同様に二種類の損失にはバイアスが生じると考えられ、その期待値は次のようにある。
このバイアスは漸近的に次の汎関数分散を
で割った値に一致することが知られている。
WAICは経験損失と汎関数分布をで割った値の和として定義される。
WAICでは現実値の計算に真の分布を必要としない。
BIC
BICを考えるときに、以下を仮定する。
真の分布は想定される確率モデルの中に含まれる
サンプルはi.i.d
は確率モデルについて必ずしも正則でなくても仮定
モデルからデータが得られる確からしさとして周辺尤度は次のように定義されます。
この周辺尤度を用いて次のような(ベイズ)自由エネルギーが定義される。
次の条件が満たされている場合、
真の分布が確率モデルに対して正則
事後分布が正規分布に近似できる
nが十分に大きい
自由エネルギーは積分のラプラス近似の手法を用いて次のように近似することができる。これがBICの定義となる。
WBIC
WBICは正則でないモデルにおいても、自由エネルギーを近似することができる。
WBICは次のように定義できる。
ここでは経験対数損失である。
WBICは逆温度がの時の事後分布における期待であると言える。
MCMCの結果から自由エネルギーを推定する方法としてブリッジサンプリングが存在する。
ブリッジサンプリング
周辺尤度はモデルが複雑になると解析的に計算することが難しくなります。
MCMCを使ったシミュレーションによる積分計算の方法が、ブリッジサンプリングです。
ブリッジサンプリングの前に周辺尤度を得る方法として、ナイーブモンテカルロ法と重点サンプリング法が存在する。
ナイーブモンテカルロ法では、MCMCで事前分布から大量の乱数パラメータを生成し、各サンプルの尤度関数の期待値をとることで周辺尤度を計算する。
この方法では、事前分布と事後分布に乖離がある場合はシミュレーションの効率が悪くなる。
重点サンプリング法は提案分布から乱数を生成し、各サンプルの尤度を事前分布と提案分布の比で調整してから平均する方法である。
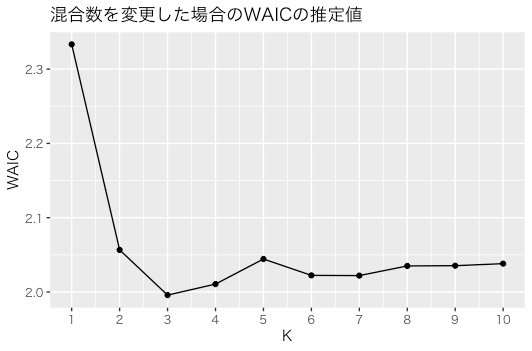 g (\theta), \hat p_{IS}(x^n) = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^R p(x^n|\hat \theta_i)\frac{\phi (\hat \theta_i)}{g(\hat \theta_i)}
}]
g (\theta), \hat p_{IS}(x^n) = \frac{1}{R} \sum_{i=1}^R p(x^n|\hat \theta_i)\frac{\phi (\hat \theta_i)}{g(\hat \theta_i)}
}]ナイーブモンテカルロ法より、効率よく計算できるが、提案分布に何を選択するのかで変わってくる。
この分布は(1)事後分布より裾が重く(2)事後分布と形状が類似しており(3)事後分布と同じ台を持ち(4)評価が容易な分布である ことが求められるとされている。
そのほかにも、一般化調和平均サンプリング法が提案されている。
この方法でも調整のために重点分布の設定を行う必要がある。
そして、ブリッジサンプリングでは、重点サンプリングと一般化調和平均サンプリングの両方のアルゴリズムの利点を取り入れた方法となっている。
具体的には、提案分布 からの乱数
と,事後分布[tex:p(\theta|xn)] からの乱数
の両者を利用する。
この提案分布では、事後分布と類似しており重なりが大きい分布が求められる。
ここではブリッジ関数である(詳細についてはよくわからず)
Rstanでの算出
混合ガウス分布において混合数を変えた時のWAICとWBICを推定する。
利用したサンプルデータ次のように生成した。
generate_bimodal_data <- function(N, m1, m2, sd1, sd2, p, seed = 42){ set.seed(seed) Y <- c(rnorm((1-p)*N, m1, sd1), rnorm(p*N, m2, sd2)) return(Y) } X <- generate_bimodal_data(500, 0,5, 1, 1, 0.3)
WAIC
WAICを算出するための対数尤度を計算しつつ混合ガウス分布を推定するモデルを次のようなものとした。
data {
int<lower=1> K;
int<lower=1> N;
vector[N] X;
}
parameters {
simplex[K] p[N];
ordered[K] mu;
vector<lower=0, upper=20>[K] sigma;
}
transformed parameters{
real theta[N,K];
for(n in 1:N)
for(k in 1:K)
theta[n, k] = log(p[n, k]) + normal_lpdf(X[n] | mu[k], sigma[k]);
}
model {
sigma ~ cauchy(0,2.5);
mu ~ normal(0,10);
for(n in 1:N)
target += log_sum_exp(theta[n]);
}
generated quantities {
vector[N] log_likelihood;
vector[K] tmp[N];
//int index;
// real X_pred;
for(n in 1:N){
for(k in 1:K){
tmp[n, k] = log(p[n, k]) + normal_lpdf(X[n] | mu[k], sigma[k]);
}
log_likelihood[n] = log_sum_exp(tmp[n]);
}
}
MCMC結果からWAICを算出する関数は次にように定義します。
WAIC <- function(log_likelihood) { training_error <- - mean(log(colMeans(exp(log_likelihood)))) functional_variance_div_N <- mean(colMeans(log_likelihood^2) - colMeans(log_likelihood)^2) waic <- training_error + functional_variance_div_N return(waic) }
また、loo packageを用いた方法でも WAICを推定してみます。
loo::waic(extract(fit_model_waic)$log_lik)$waic/(2*length(df))
それぞれの結果は次にようになりました。
> res_mcmc_loop_waic k waic waic.loo 1 1 2.336001 2.336002 2 2 2.061759 2.061882 3 3 2.002740 2.002835 4 4 2.009547 2.009646 5 5 2.021851 2.021954 6 6 2.016386 2.016470 7 7 2.015118 2.015195 8 8 2.018240 2.018328 9 9 2.018385 2.018463 10 10 2.016807 2.016873
対数から直接計算したものとloo::waicで算出したものはほぼ一緒になった。
対数から計算したWAICをグラフ化してみると次のようになった。
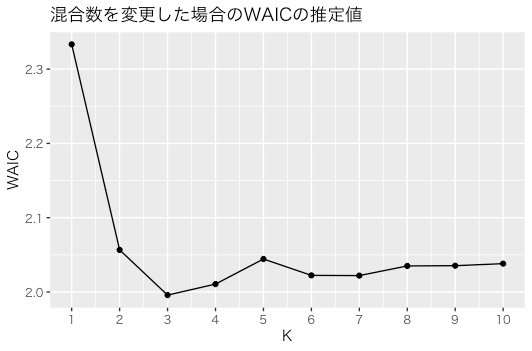
WBIC
WBICの計算はstanコードを変更することによる算出方法とbridgesampling packageを利用したブリッジサンプリングによる算出方法を試す。
対数情報からWBICを算出する関数は次にように定義します。
WBIC <- function(log_likelihood){ -mean(rowSums(log_likelihood)) }
この関数を利用するためには、逆温度が1/log(データ数)の時の事後分布が必要になるため、上記のstanコードのmodelブロックを次のように変更する必要がある。
model {
sigma ~ cauchy(0,2.5);
mu ~ normal(0,10);
for(n in 1:N)
target += 1/log(N) * log_sum_exp(theta[n]);
}
対数尤度から計算したWBICの変化をみてみました。
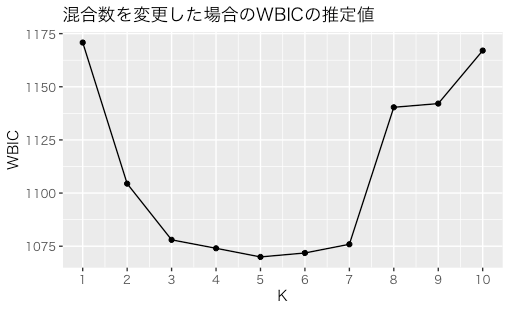
bridge samplingによるWBICの推定を行う関数を次のように定義した。
WBIC.bs <- function(model){ bs <- bridge_sampler(model, method = "warp3") return(-logml(bs)) }
また、MCMCを実行する実行する時のiter数はかなり大きな値を設定しないと、bridge samplingを行う際にエラーとなってします。
今回はiter=10000, wurmup=1000とした。
実行時間がかなりかかるため、K=2,3の場合のみを計算し、事後対数からえたWBICと比較した。
| WBIC | WBIC(BS) | |
|---|---|---|
| K=2 | 1104.143 | 1043.078 |
| K=3 | 1445.512 | 1355.124 |
二つの方法で一致しませんでした。
他の簡単なサンプルで実行しましたが、やっぱり一致しませんでした。
